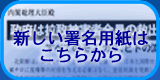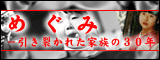マルズキ国連北朝鮮人権問題担当特別報告者と懇談?家族会・救う会(2012/01/20)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2012.01.20)
昨日、1月19日、家族会・救う会は、来日したマルズキ・ダルスマン
(Marzuki Darusman)国連北朝鮮人権問題担当特別報告者と面会した。マルズキ
氏は今年3月に、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況について、国連人権理事会に
報告書を提出するが、そのための調査で来日した。同氏は、ウィティット・ムン
タボーン氏の後任で、今回が昨年に続き2回目の面会となった。
家族会からは、飯塚繁雄代表、横田滋・早紀江前代表夫妻、増元照明事務局長
が参加、救う会からは平田隆太郎事務局長が参加、政府拉致問題対策本部、外務
省も参加した。
懇談の概要は下記の通り。
■マルズキ国連北朝鮮人権問題担当特別報告者と懇談?家族会・救う会
マ氏 昨年3月に国連に報告した後、北朝鮮非難決議で賛成国が増加した。国際
社会が理性を深めた証であり、さらに北朝鮮にプレッシャーをかけられると考え
ている。特に、北朝鮮で新政権ができたこのタイミングはプレッシャーが問題を
前進させると考えている。できる限りの努力をしたいので、助言してほしい。
また今回、新潟を訪問し、横田めぐみさんの拉致現場を歩いた。何十年経って
も、解決への強い決意と真実を暴く希望が生き生きと息づいているとの印象を受
け、また支援者の活動や家族の痛みに深く心を動かされた。
また、本日玄葉外相と面会したが、拉致問題が日本の最大の関心事であると感
じた。それらのことを反映する報告書をまとめたいと考えている。
飯塚 拉致問題は深いところまで理解されていると思う。しかし、いかに早く解
決するかが課題だ。その戦略は政府が責任を持ってやるべきだが、北朝鮮はした
たかな態度で未だに「拉致問題は解決済み」と言っている。北朝鮮にプレッシャー
をかけるとの言葉を嬉しく思う。
北朝鮮は今不安定で周辺国や日本のプレッシャーが必要だ。国連総会の北朝鮮
人権非難決議で賛成国が増えたのは嬉しいが、中国の北朝鮮に対する影響力が大
きい。中国を初めとする反対国への説得ができないかと思う。各国からプレッシャー
をかけてほしい。
マ氏 3月にジュネーブに報告書を出すが、決議反対国の代表、北朝鮮による被
害国の代表にも会う予定だ。中国は鍵になる国だ。できれば訪中し協議したい。
その取り組みでさらに北朝鮮にプレッシャーをかけたいと思っている。
横田滋 駐日米大使も、「拉致現場に行くと実感が違う。ブッシュ大統領に報告
した」と言っておられた。それもあって、大統領との面会が実現し、ありがたかっ
た。北朝鮮も加盟している児童の権利条約には、子どもを連れていってはいけな
いなどとあるが、北朝鮮は無視している。
また、韓国の女性議員朴宣映(パク・ソンヨン)さんが来てくださり、200
5年頃めぐみが生存していたと脱北者から聞いたと伝えてくださった。その脱北
者呉吉男さんは、北朝鮮に残された妻の申淑子さんと娘たちを救出する活動をし
ているのでぜひ報告してほしい。
マ氏 呉吉男氏にはソウルで会った。
横田早紀江 拉致問題が早く解決しないと被害者も歳をとる。我々は、どんな暮
らしをしているのか分からない。病気になっているのではないかとか、各家族が
心配している。めぐみの場合は34年になり、家族も高齢化している。早く状況
が分かるように政府にお願いしているが分からない。どこにいるのか、どうして
いるのか、そういう思いの生活が長く続いている。小さな情報でも得たいと思う。
マ氏 北朝鮮に、被害者の調査を再開させることが大事だ。
増元 我々は日本人拉致被害者は約100人と推計しているが、事実として確認
できていない。金正日の死が変化になり、チャンスになることを望む。しかし、
変化により被害者の処遇が変化したりパージされたりする可能性もあるので、1
年以内に解決しなければだめだという思いだ。
北朝鮮問題は中国問題に移行したと思う。中国が影響力を及ぼすことは間違い
ない。中国は国連安保理事国なのに、決議を無視して北朝鮮を擁護している。ま
た脱北者を保護せず、強制的に北朝鮮に返すので、関係情報を取る障害になって
いる。
国連決議に基づき、国連北朝鮮人権問題担当特別報告者が生まれて7年になる
が、北朝鮮状況には変化がない。この状況を打破しないといけない。国連は北朝
鮮を非難しつつ、他方で援助しているので、これは北朝鮮に対し誤ったメッセー
ジになっているのではないか。決議賛成国が義務を負うようにしないと北朝鮮は
変わらない。
マ氏 拉致被害者数が日本政府認定の17名をはるかに超えるのなら、新たな側
面が生まれてくると思う。政治的だけでなく法律的にも重大だ。
平田 国連のFAOやWFPの北朝鮮の食糧事情報告は現実の収穫量より多めに報告し
ており、現実はさらに厳しいということを昨年はお伝えしたが、その状況がさら
に悪化しており、経済的にも厳しい状況になった。特に、国内で外貨使用が禁じ
られたことの影響が大きいと思われる、北朝鮮が不安定化しており、チャンスと
リスクが生まれようとしている。
チャンスは待つだけでなく、仕掛けるべきで、プレッシャーはもちろんそれ以
外の手段も考えるべきだ。また、北朝鮮が崩壊して被害者が混乱に巻き込まれる
というリスクにも対応を検討しておくべきだ。
マ氏 金正恩政権の変化を見る必要がある。個人的印象だが、国連がとってきた
態度は、北朝鮮がまもなく破綻すると見越していたのではないかと思う。しかし、
破綻したふりだけで国家は破綻していない。食糧問題は重要な問題だが、どう出
るか。国民のニーズを満たせていない。周辺諸国の食糧支援には、拉致問題を認
識してもらう必要があるが、直接拉致と支援を関係づけるのはよくないと思う。
政府 野田総理は、在京の大使などに、拉致問題は、「第1に厳然たる事実であ
る。第2に依然として未解決の問題である。第3にグローバルな問題である」と
語り、強い意思を示した。マスコミも野田総理のやる気を感じているようだ。
増元 安倍総理が、温家宝首相に、中国人拉致問題について言及したが、その後
中国は自国民の拉致被害について公にしていない。なかったことにする姿勢だ。
中国籍の朝鮮族も多数拉致されているが無視されている。
マ氏 中国政府の人には、ジュネーブとニューヨークで会ったが、中国訪問の意
志を伝えるつもりだ。中国人拉致問題も今後見ていかなければと思う。国連北朝
鮮人権状況特別報告者は今年で7年目になるが、多くの情報を蓄積してきた。こ
れは大きな意味がある。
今日は松原(拉致問題担当)大臣の決意もうかがった。「このままでは北朝鮮
は世界の孤児になる」と言っていた。
※国連北朝鮮人権状況特別報告者は、2004年の国連人権委員会(現在の国連人権
理事会)で採択された北朝鮮人権状況決議に基づき任命された。同特別報告者は、
北朝鮮の人権状況について報告する任務を有する独立資格の個人である。
以上
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
■野田首相にメール・葉書を
首相官邸のホームページに「ご意見募集」があります。
下記をクリックして、ご意見を送ってください。
[PC]https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
[携帯]https://www.kantei.go.jp/k/iken/im/goiken_ssl.html?guid=ON
葉書は、〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣 野田佳彦殿
■救う会全国協議会ニュース
発行:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(救う会)
TEL 03-3946-5780 FAX 03-3946-5784 http://www.sukuukai.jp
担当:平田隆太郎(事務局長 info@sukuukai.jp)
〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-11-905
カンパ振込先:郵便振替口座 00100-4-14701 救う会
みずほ銀行池袋支店(普)5620780 救う会事務局長平田隆太郎
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
昨日、1月19日、家族会・救う会は、来日したマルズキ・ダルスマン
(Marzuki Darusman)国連北朝鮮人権問題担当特別報告者と面会した。マルズキ
氏は今年3月に、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況について、国連人権理事会に
報告書を提出するが、そのための調査で来日した。同氏は、ウィティット・ムン
タボーン氏の後任で、今回が昨年に続き2回目の面会となった。
家族会からは、飯塚繁雄代表、横田滋・早紀江前代表夫妻、増元照明事務局長
が参加、救う会からは平田隆太郎事務局長が参加、政府拉致問題対策本部、外務
省も参加した。
懇談の概要は下記の通り。
■マルズキ国連北朝鮮人権問題担当特別報告者と懇談?家族会・救う会
マ氏 昨年3月に国連に報告した後、北朝鮮非難決議で賛成国が増加した。国際
社会が理性を深めた証であり、さらに北朝鮮にプレッシャーをかけられると考え
ている。特に、北朝鮮で新政権ができたこのタイミングはプレッシャーが問題を
前進させると考えている。できる限りの努力をしたいので、助言してほしい。
また今回、新潟を訪問し、横田めぐみさんの拉致現場を歩いた。何十年経って
も、解決への強い決意と真実を暴く希望が生き生きと息づいているとの印象を受
け、また支援者の活動や家族の痛みに深く心を動かされた。
また、本日玄葉外相と面会したが、拉致問題が日本の最大の関心事であると感
じた。それらのことを反映する報告書をまとめたいと考えている。
飯塚 拉致問題は深いところまで理解されていると思う。しかし、いかに早く解
決するかが課題だ。その戦略は政府が責任を持ってやるべきだが、北朝鮮はした
たかな態度で未だに「拉致問題は解決済み」と言っている。北朝鮮にプレッシャー
をかけるとの言葉を嬉しく思う。
北朝鮮は今不安定で周辺国や日本のプレッシャーが必要だ。国連総会の北朝鮮
人権非難決議で賛成国が増えたのは嬉しいが、中国の北朝鮮に対する影響力が大
きい。中国を初めとする反対国への説得ができないかと思う。各国からプレッシャー
をかけてほしい。
マ氏 3月にジュネーブに報告書を出すが、決議反対国の代表、北朝鮮による被
害国の代表にも会う予定だ。中国は鍵になる国だ。できれば訪中し協議したい。
その取り組みでさらに北朝鮮にプレッシャーをかけたいと思っている。
横田滋 駐日米大使も、「拉致現場に行くと実感が違う。ブッシュ大統領に報告
した」と言っておられた。それもあって、大統領との面会が実現し、ありがたかっ
た。北朝鮮も加盟している児童の権利条約には、子どもを連れていってはいけな
いなどとあるが、北朝鮮は無視している。
また、韓国の女性議員朴宣映(パク・ソンヨン)さんが来てくださり、200
5年頃めぐみが生存していたと脱北者から聞いたと伝えてくださった。その脱北
者呉吉男さんは、北朝鮮に残された妻の申淑子さんと娘たちを救出する活動をし
ているのでぜひ報告してほしい。
マ氏 呉吉男氏にはソウルで会った。
横田早紀江 拉致問題が早く解決しないと被害者も歳をとる。我々は、どんな暮
らしをしているのか分からない。病気になっているのではないかとか、各家族が
心配している。めぐみの場合は34年になり、家族も高齢化している。早く状況
が分かるように政府にお願いしているが分からない。どこにいるのか、どうして
いるのか、そういう思いの生活が長く続いている。小さな情報でも得たいと思う。
マ氏 北朝鮮に、被害者の調査を再開させることが大事だ。
増元 我々は日本人拉致被害者は約100人と推計しているが、事実として確認
できていない。金正日の死が変化になり、チャンスになることを望む。しかし、
変化により被害者の処遇が変化したりパージされたりする可能性もあるので、1
年以内に解決しなければだめだという思いだ。
北朝鮮問題は中国問題に移行したと思う。中国が影響力を及ぼすことは間違い
ない。中国は国連安保理事国なのに、決議を無視して北朝鮮を擁護している。ま
た脱北者を保護せず、強制的に北朝鮮に返すので、関係情報を取る障害になって
いる。
国連決議に基づき、国連北朝鮮人権問題担当特別報告者が生まれて7年になる
が、北朝鮮状況には変化がない。この状況を打破しないといけない。国連は北朝
鮮を非難しつつ、他方で援助しているので、これは北朝鮮に対し誤ったメッセー
ジになっているのではないか。決議賛成国が義務を負うようにしないと北朝鮮は
変わらない。
マ氏 拉致被害者数が日本政府認定の17名をはるかに超えるのなら、新たな側
面が生まれてくると思う。政治的だけでなく法律的にも重大だ。
平田 国連のFAOやWFPの北朝鮮の食糧事情報告は現実の収穫量より多めに報告し
ており、現実はさらに厳しいということを昨年はお伝えしたが、その状況がさら
に悪化しており、経済的にも厳しい状況になった。特に、国内で外貨使用が禁じ
られたことの影響が大きいと思われる、北朝鮮が不安定化しており、チャンスと
リスクが生まれようとしている。
チャンスは待つだけでなく、仕掛けるべきで、プレッシャーはもちろんそれ以
外の手段も考えるべきだ。また、北朝鮮が崩壊して被害者が混乱に巻き込まれる
というリスクにも対応を検討しておくべきだ。
マ氏 金正恩政権の変化を見る必要がある。個人的印象だが、国連がとってきた
態度は、北朝鮮がまもなく破綻すると見越していたのではないかと思う。しかし、
破綻したふりだけで国家は破綻していない。食糧問題は重要な問題だが、どう出
るか。国民のニーズを満たせていない。周辺諸国の食糧支援には、拉致問題を認
識してもらう必要があるが、直接拉致と支援を関係づけるのはよくないと思う。
政府 野田総理は、在京の大使などに、拉致問題は、「第1に厳然たる事実であ
る。第2に依然として未解決の問題である。第3にグローバルな問題である」と
語り、強い意思を示した。マスコミも野田総理のやる気を感じているようだ。
増元 安倍総理が、温家宝首相に、中国人拉致問題について言及したが、その後
中国は自国民の拉致被害について公にしていない。なかったことにする姿勢だ。
中国籍の朝鮮族も多数拉致されているが無視されている。
マ氏 中国政府の人には、ジュネーブとニューヨークで会ったが、中国訪問の意
志を伝えるつもりだ。中国人拉致問題も今後見ていかなければと思う。国連北朝
鮮人権状況特別報告者は今年で7年目になるが、多くの情報を蓄積してきた。こ
れは大きな意味がある。
今日は松原(拉致問題担当)大臣の決意もうかがった。「このままでは北朝鮮
は世界の孤児になる」と言っていた。
※国連北朝鮮人権状況特別報告者は、2004年の国連人権委員会(現在の国連人権
理事会)で採択された北朝鮮人権状況決議に基づき任命された。同特別報告者は、
北朝鮮の人権状況について報告する任務を有する独立資格の個人である。
以上
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
■野田首相にメール・葉書を
首相官邸のホームページに「ご意見募集」があります。
下記をクリックして、ご意見を送ってください。
[PC]https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
[携帯]https://www.kantei.go.jp/k/iken/im/goiken_ssl.html?guid=ON
葉書は、〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣 野田佳彦殿
■救う会全国協議会ニュース
発行:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(救う会)
TEL 03-3946-5780 FAX 03-3946-5784 http://www.sukuukai.jp
担当:平田隆太郎(事務局長 info@sukuukai.jp)
〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-11-905
カンパ振込先:郵便振替口座 00100-4-14701 救う会
みずほ銀行池袋支店(普)5620780 救う会事務局長平田隆太郎
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆