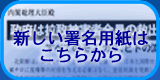各地の救出運動の現状と北朝鮮最新情勢から全拉致被害者の即時一括救出の方途を考える拉致問題セミナー
◆不義に対しては断固として立ち上がるのが日本人
熊谷美加(救う会佐賀事務局次長)
救う会佐賀事務局次長の熊谷美加と申します。宜しくお願いいたします(拍手)。配布資料もご覧ください。
「救う会佐賀」が正式に発足したのは、平成24年です。会長は北朝鮮帰還事業で北に渡った日本人妻の帰国運動に尽力してきた大原巖が務めています。
佐賀県での活動では、次の2つのことを大切にしてきました。1つ目は行政との連携、2つ目は拉致問題を風化させないための教育現場での啓発活動の推進です。
まず、行政との連携についてお話しします。私たちは、県の拉致問題担当部署である「人権同和対策課(人権課)」と「北朝鮮拉致問題早期解決促進議員連盟(拉致議連)」の議員の先生方や議会事務局の方の元へ、定期的にお伺いし、相談を重ね、活動を共にしてきました。
毎年行政が行っている「拉致問題を考える県民の集い」は、救う会佐賀も主催団体です。
平成25年に、佐賀県下、全20市町で、拉致問題の即時解決を願う意見書を採択し、平成26年には全市町でパネル展示を実現しました。当時の人権課の職員の方は、横浜まで赴き、工作船の展示を見る等調査して、佐賀県独自のパネルを作成して下さいました。この方と一緒に私たちも各市町に足を運び、展示をして、署名を行ったのは、今でもとてもありがたいことだったと感じています。現在もこの時のパネルは使っています。
つぎに教育現場での啓発活動の推進についてお話しします。平成28年には教職員対象の研修会を県内2会場で開催。平成29年には舞台劇「めぐみへの誓い」を上演、小中学生も観劇しました。また、この年佐賀県人権教育・啓発基本方針第二次改訂が行われるのを受け、パブリックコメントの提出を呼びかけ、拉致問題を人権教育の重点項目として明記しました。さらに、熊本県、救う会熊本と協力し、副読本「とりもどしたい家族の絆―熊本県の拉致被害者松木薫さん」を作成し、熊本県内すべての小中学生への配布を実現しました。資料の裏に副読本の写真をつけています。
これは救う会熊本の方が斎藤文代さんに取材をした内容を元に、絵と文、構成を、私が担当しました。予算は熊本県がつけて下さいました。この副読本は熊本県のホームページからどなたでもダウンロードして活用頂けるようになっています。
令和3年は、大きく3つの活動に取り組んでいます。1つ目は映画「めぐみへの誓い」上映運動です。1週間という限られた期間でしたが、111名もの方が鑑賞して下さいました。
2つ目は県庁での署名活動です。私たちは結成当時より、毎月署名活動を街頭で行ってきました。コロナ感染拡大のため近年は中断していましたが、議連と人権課職員の方々にご協力頂き、今年は5月と11月の2回、県庁ロビーで行うことができました。職員の中には初めて署名活動をする側に立って、チラシを受け取ってもらうこと、署名を書いてもらうことの難しさと嬉しさを感じたという声が聞かれました。
この際、ブルーリボンも販売し、多くの方にご購入頂けました。実は、先日、人権課の方より、新たに3つ、ブルーリボンを分けてくれと連絡がありました。知事と副知事3人分で、ポケットマネーでのお求めでした。これは11月13日の「即時一括帰国を求める 国民大集会」で、「12月の北朝鮮人権週間に、各首長、議員にバッジをつけ意思を示そう」と決議されたのを受け、職員が知事室に話をしに行かれた結果でした。
3つ目は、拉致議連との協同プロジェクト「佐賀県版 拉致問題啓発リーフレット」の作成です。きっかけは、議連の会長より議会事務局を通じて「予算を有効に使う方法を考えて」と相談を受けたことです。救う会佐賀の事務局で話し合い、リーフレット作成をご提案し、始まりました。これは、小学校高学年、中高生を対象とし、補助教材として学校での活用を目指す物です。配布は来年4月より開始予定です。この教材も佐賀県に留まらず他の自治体でも自由に活用して頂きたいと考えています。
現在私たちは県民全体への啓発活動はもちろんですが、小中高校生への啓発に、より重点をおいています。それは、子どもたちにこそ拉致問題を見逃さない意識を持ってほしいと強く願っているからです。
私自身のことをお話しします。私が拉致問題を知ったのは平成14年、中学2年生の時でした。拉致された人がいて、北朝鮮から戻ってきた。でも、亡くなった人もいるらしい。「かわいそうだ」と思いました。しかし、拉致された人とその家族はかわいそうだけど、自分は大丈夫。テレビの向こうで起きていることだからと切り離して、どこか自分を安心させていたように思います。
私が変わるきっかけになったのは、大学1年生の時に拉致被害者ご家族が福岡で講演されるのを聞いてからです。その際に平野フミ子さんと直接お話しする機会を得ました。妹を拉致されるという想像できないような苦境の中にありながら、平野さんは「皆さんと会えて幸せです」と言われました。自分に何ができるのだろうかと思っていたけれど、自分にも何かできるのではないか、そう思いました。
そこから、新潟や鹿児島の拉致現場に行ったり、署名活動や講演会を開催したりしました。また、世界で最も拉致被害者が多い韓国に赴き、韓国人拉致被害者ご家族や脱北青年らにも会ってこの問題を考えました。現場に行き、当事者の話を聞く。そこから問題を考える経験を積み重ねて、私にとり拉致問題は他人事ではなくなりました。
これは安全保障上の問題に留まるものではないと私は思います。日本という一つの共同社会に属する一人一人の精神の問題が本質にあります。
平成14年、上皇后陛下はお誕生日を迎えられた際に、次のようにおっしゃっています。
「悲しい出来事についても触れなければなりません。小泉総理の北朝鮮訪問により,一連の拉致事件に関し、初めて真相の一部が報道され、驚きと悲しみと共に、無念さを覚えます。何故私たち皆が、自分たち共同社会の出来事として、この人々の不在をもっと強く意識し続けることが出来なかったかとの思いを消すことができません。今回の帰国者と家族との再会の喜びを思うにつけ、今回帰ることのできなかった人々の家族の気持ちは察するにあまりあり、その一入の淋しさを思います」。
「驚き、悲しみ、無念さ」、そして「一入の淋しさ」というお言葉の一つ一つから、拉致被害者とそのご家族に深く思いを致される上皇后陛下のご姿勢が偲ばれます。私は中学2年生のあの時、戻らなかった人を思って「淋しい」とはとうてい思えませんでした。「淋しい」とは、家族が戻らなかった拉致被害者ご家族の側に立たないと出てこない言葉でだと思います。
人の苦しみ、悲しみを知りながら、見過ごすのではなく、その人の側に立ち、寄り添い、不義に対しては断固として立ち上がるのが日本人である。私はこの14年間の活動を通じて出会った方々に、皆様に、日本人として、人間として大切なことは何か教えて頂きました。今度は私が子どもたちに示す番だと思っています。
最近感激したことがあります。昨年佐賀で開催した拉致問題の講演会で、私は急遽登壇し、60分近く話すことになりました。必死に原稿をその場で書き上げ、なぜ自分が拉致問題を考え、解決のために活動するのかを400名を超える方の前で語りました。
そして先月、リーフレット作成の県庁でのミーティングで、教育庁の担当の方より、「私はあの時、熊谷さんの話を聞いて、なぜ拉致被害者家族でもないのに、こんなに真剣なんだろうと思ったんです。それから、この問題に関心をより寄せるようになりました」と言って頂いたのです。この方は、昨年の講演会をきっかけに、映画「めぐみへの誓い」の映画も観て、県庁内での署名活動に2回とも協力してくださいました。リーフレット作成にあたり、「現場でかならず活用されるものにしましょう」と力強い言葉も頂いております。
政府認定の拉致被害者がいない佐賀県だからこそ、声をあげていく。自分の自治体に拉致被害者がいるかいないかは関係ありません。これは日本の問題、日本人である私たちが解決する問題です。オールジャパンでの拉致問題即時解決の実現のために、佐賀県でこれからも頑張り抜きます。ご静聴ありがとうございました(拍手)。
西岡 実は蓮池薫さんが講演することになっていたのですが、飛行機が遅れたか何かで着かなかったのです。60分あいてしまう。「この際お前が行け」ということになりました。全然準備していなかったのに、60分話をした。そしてら聞いていた人から、「こういうことがあった」とフェイスブックで書いた。それを見て、これはすごいと思って来てもらったのです。
私は大学生の時から知っているんです。そうしたらもっと勉強したいということで韓国まで行って、拉致被害者家族とも会ったのですが、その前に韓国の国立墓地に行って兵士たちに敬意を表したと聞きました。韓国では「救う会」みたいな組織がなくて、家族だけでやっているので、韓国の家族の人たちが感激しちゃって、そしたら今度は彼女たちを呼んで全国縦断講演会をやるなど、そういうことを独自にずっと学生時代にやってくれた方で、今は塾の先生をしながら救う会佐賀で活動をしています。まだ救う会佐賀がない時から活動しているわけです。
風化させないことはみんながどこでもできるのです。今話がありましたが、被害者がいる県だけでなく、家族だけのことでもない。日本人のことです。
今皇后陛下の「おことば」の話がありましたが、これは5人の被害者が「一時帰国」した時でした。私は9月10日、11日と東京に泊まって、11日の夜小浜に地村さんと一緒に行って地村さんの家に泊まりました。その日の夜、地村さんのお父さんは1階で寝ていて、2階に地村保志さんとお兄さんがいました。
お兄さんが、「久しぶりだからお酒でも飲もう」とお酒を飲んでいて、私はその向かいの部屋にいました。夜中の3時頃ですね、お兄さんがドンドンとドアをたたいて、「先生、日本政府が守ってくれるなら日本に残りたいと言っています」と言いました。でも家族が向こうにいる。そこで私は安倍さんに電話した。先ほど、「本人に意思があった」とおっしゃったのはそういうことです。
そしてその日の朝刊に出ていた。「残りたい」と言ったのですが、「本当に日本政府が守ってくれるのか、子どもたちを取り戻してくれるのか」と思ったそうです。皇后陛下の「おことば」、松本さんの質問と今の話と併せて思い出しました。
日本人は味方なんだと。5人の人が日本に残ることも戦いだったのです。彼らは、「日本に行ったら、あなたたちはテロに加担した人間だから」と言ったそうです。そうではなく、暖かく迎えてくれた。そこで、子どもたちは向こうにいるのに、日本を信じて残る決断をしたのです。
では、先ほど壇上でもう少し話すはずだった小坪さんにお願いします。